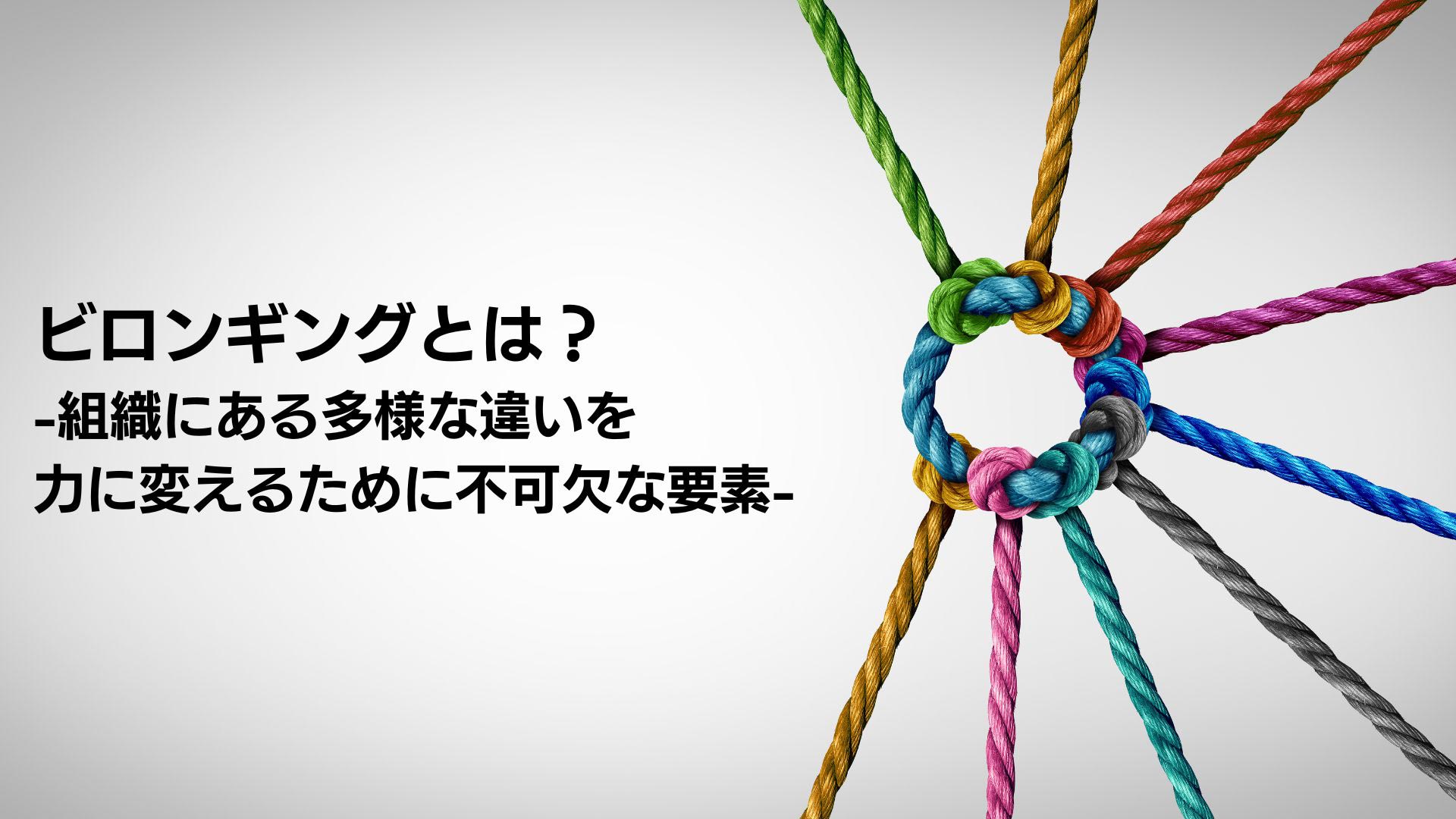
近年、企業における「ビロンギング(Belonging)」の重要性が高まっています。ビロンギングとは、組織で働く一人ひとりが「自分らしくいられながら自分の強みをチームで活かせている」と実感できる愛着のある帰属意識のことです。ビロンギングは、多様な人、多様な価値観が存在する現代において、それらを排除せずに、チームの力に変えるための不可欠な要素です。ここではビロンギングの本質と、それが組織にもたらす価値について、多様な違いを組織の力に変えるための学び「インクルーシブ・コミュニケーター」でお伝えしている内容をふまえて解説していきます。
ビロンギング(belonging)とは「所属」という意味であり、簡単に言うと「帰属意識」のことです。
古英語の「belangian」に由来し、「be(存在する)」と「long(長く)」という要素から成り立っています。
近年のビジネス・企業組織におけるビロンギングとは、組織で働く一人ひとりがその人らしくいることができると実感し、自分らしさを活かしながらチームにもっと関わりたいと思えることです。つまり、ビロンギングとは、単なる所属意識ではなく、個人的な感情や愛着を伴った帰属意識のことです。
コロナ禍を経て、リモートワークやハイブリッドワークが一般化し、従来の「同じ場所で働く」という働き方の形態が大きく変化し多様化しています。物理的な距離が広がる中で、心理的なつながりも同時に希薄になり、その組織で働くことの意味が失われて、やりがいの喪失や離職に繋がっています。また、副業・兼業の解禁やジョブ型雇用の導入など、従来の日本型雇用システムからの転換も進んでおり、新しい形での組織との結びつきが求められています。
働き方だけでなく、働く目的も多様化しています。
一人ひとり異なる価値観を持っていることが尊重されるようになり、“お金を稼ぐこと”だけが仕事や人生のすべてではなくなりました。
個人が個人の求める生きがいややりがいを求めて、それにフィットした仕事や組織を選択できるようになっています。そのような価値観を無視して、組織の利益追求を第一とする価値観を強要するような組織では、多様な価値観を持つ人の力を引き出すことはできなくなっています。
多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)は、現代の組織において重要な価値観となっています。しかし、これらの要素を単に掲げるだけでは、組織の真の強みとはなりません。
ビロンギングは、DE&Iの取り組みを実効性のあるものとし、組織のパフォーマンス向上につなげるための重要な架け橋となります。
ビロンギングは、それ単体では成立せず、DE&Iと緊密に関わっている要素の一つです。その人らしさ・その人の価値観などの多様性を認め(Diversity)、多様な違いによる不公平を取り除き公平な機会を提供し(Equity)、誰もが参加できる環境を整えられ(Inclusion)、その人らしくいられながら組織に関わりたいと思える愛着のある帰属意識があることで(Belonging)、その組織で多様性が力となっていくのです。
近年、DE&Iにビロンギングが加わり、DEIBと表記する企業が増えてきている背景には、このようなDE&Iとビロンギングが関係していることが意識されているからです。

ビロンギングという新しい概念に触れた時、“単なる「忠誠心」と何が違うの?”や“エンゲージメントと一緒ではないの?”と思う人もいるかもしれません。
ビロンギングは忠誠心やエンゲージメントなどと重なる部分もありながらも、独自の観点がある概念であるため、関連した概念を整理してみましょう。

ロイヤルティは組織への忠誠心を表す概念です。昭和の日本的企業やそこで働く人が重視していた“愛社精神”がロイヤルティにあたります。高度経済成長期のような、社会や組織全体で直線的な成長が見通せて、物質的な豊かさを求めることが価値観として共有され、さらにそれを企業組織側が働く人に提供できることが約束されているような時代であれば、組織で働く人は“滅私奉公”の精神を求められていても、多少の不満があっても従うことが成立した関係性でした。しかし、現代は不確実な未来、多様な価値観により、企業が一方的に忠誠心を求めることは困難になっています。
一方、ビロンギングは組織との情緒的なつながりを重視します。ロイヤルティが組織への一方向的な忠誠を示すのに対し、ビロンギングは組織と個人、そして周囲の人も含めた相互的な関係性を重視します。
コミットメントは仕事への「関与」や「責任」を示します。自分が任された仕事とそこで求められる成果に対してどれだけの熱量をもって取り組んでいるかの度合いです。コミットメントの焦点は、組織よりも仕事に対してあてられることが多いです。また、組織と、そこでは働く人との関係性という観点はなく、あくまで個人の仕事と成果に対する関わり具合です。
エンゲージメントは「契約」や「約束」を意味します。組織が働く人に対して求める仕事の責任と、それに対する組織と人との関わり度合がエンゲージメントです。このことからビロンギングにはエンゲージメントの要素も含んでいると言えますが、エンゲージメントが組織に紐づかずに、プロジェクトや仕事に紐づくこともあります。このため、プロジェクトが終われば組織とのつながりがなくなるケースや、仕事へのエンゲージメントは高くても自分の求めている仕事ができれば、その組織に所属する必然性がない、ということも起こりえます。
モチベーションとは「動機」のことであって、個人の行動を促す原動力です。このため、組織や人との関わりという観点はありません。ビロンギングは、このモチベーションを持続的なものとする重要な要素となります。ビロンギングが醸成された組織は、そこで働く人の内発的動機づけが高まり、より自律的な行動を取ることができるようになります。
ここまで説明したビロンギングの関連概念を図式化すると以下のように表せます
Harvard Business Reviewの研究によると、強いビロンギング感を持つ従業員は、そうでない従業員と比較して以下のような特徴を示すことが明らかになっています。
参考:The Value of Belonging at Work(外部サイト)
ビロンギングが企業にもたらす影響について、Gallup社の調査でも同様の結果が出ています。
企業組織で働く人が自分の意見が評価され、組織に影響を与えていると感じることが、帰属意識を高めます。しかし、Gallupの調査によれば、米国の従業員のうち、自分の意見が尊重されていると感じているのは3割に過ぎません。この割合を6割に引き上げることで、離職率の27%低下、安全性の40%向上、生産性の12%向上すると述べています。
また、職場での深い人間関係は、信頼感や安心感を生み出し、組織で働く人のエンゲージメントを高めます。調査では、職場に「親友」がいると答えた人は、業績が向上する傾向があることが示されています。この割合を2割から6割に増やすことで、安全性の36%向上、顧客エンゲージメントの7%向上、利益の12%増加が見込まれます。
心理的安全性は、ビロンギングの土台となる重要な要素です。自分の意見や考えを自由に表明でき、失敗を恐れずにチャレンジできる環境があってこそ、自分がチームや組織に意味のある存在であると感じることができるビロンギングにつながります。
組織やチームのリーダーには、この心理的安全性を確保するための環境整備や意識的取り組みが求められます。
無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)は、ビロンギングを阻害する大きな要因となります。
多様な違いや価値観に対してアンコンシャス・バイアスがあることで、自分らしさを仕事で発揮することができなくなります。
組織メンバー全員が自身のバイアスを認識し、それを克服するための努力を続けることが重要です。
特に、採用や評価の場面では、このバイアスの影響を最小限に抑える仕組みづくりが必要です。
組織の存在意義(パーパス)は、ビロンギングを強化する重要な要素です。
働くことに対して多様な価値観が存在する現代では、企業の利益追及を第一とした価値観では、人はつながることができません。もちろん特定の個人の思惑に振り回されるようではチームはまとまりません。
なぜ自分たちがこの組織にいるのか、という共通の思い:パーパスでチームの連帯が生まれます。
メンバー全員が共感できる明確なパーパスがあることで、組織との情緒的なつながりが強まります。また、個人の価値観と組織のパーパスが合致することで、より強いビロンギングが生まれます。
そしてこれら3つの要素は独立してビロンギングに影響をもたらしているのではなく、それぞれ相互に影響しあっている関係です。
どれか一つが欠けてもビロンギングは成り立たないため、ビロンギングの醸成には複層的な取り組みが必要であることが分かります。
従来、これらは関連した取り組みとは認識されていないこともありましたが、インクルーシブ・コミュニケーターの学習で、これらを体系的に取り扱っている理由がここにあります。

ビロンギングは、多様な価値観が存在する現代の企業組織において不可欠な要素となっています。多様な人が活躍する環境において、一人ひとりが「自分はここに属して貢献できている」と実感できることは、個人の生きがいと組織の発展の両方に寄与します。
ビロンギングを高めるためには、心理的安全性の確保、アンコンシャス・バイアスへの対応、パーパスの共有など、複数の要素に取り組む必要があります。これらの取り組みを通じて、組織で働く一人ひとりが自分らしさを発揮して活躍できる組織づくりを進めることが、これからの時代において重要となるでしょう。
ビロンギングの醸成は個人の意識だけでなくチームとしての環境整備も必要になります。
意識と環境を変えていく取組みはインクルーシブ・コミュニケーターの学びの中でテキスト・動画だけでなく、ワークシートでも実践的に学べるようになっています。
チームでビロンギングの重要性を共有していくためには、共通の学習を進めていくことも重要です。法人・団体受講についてお気軽にお問い合わせください